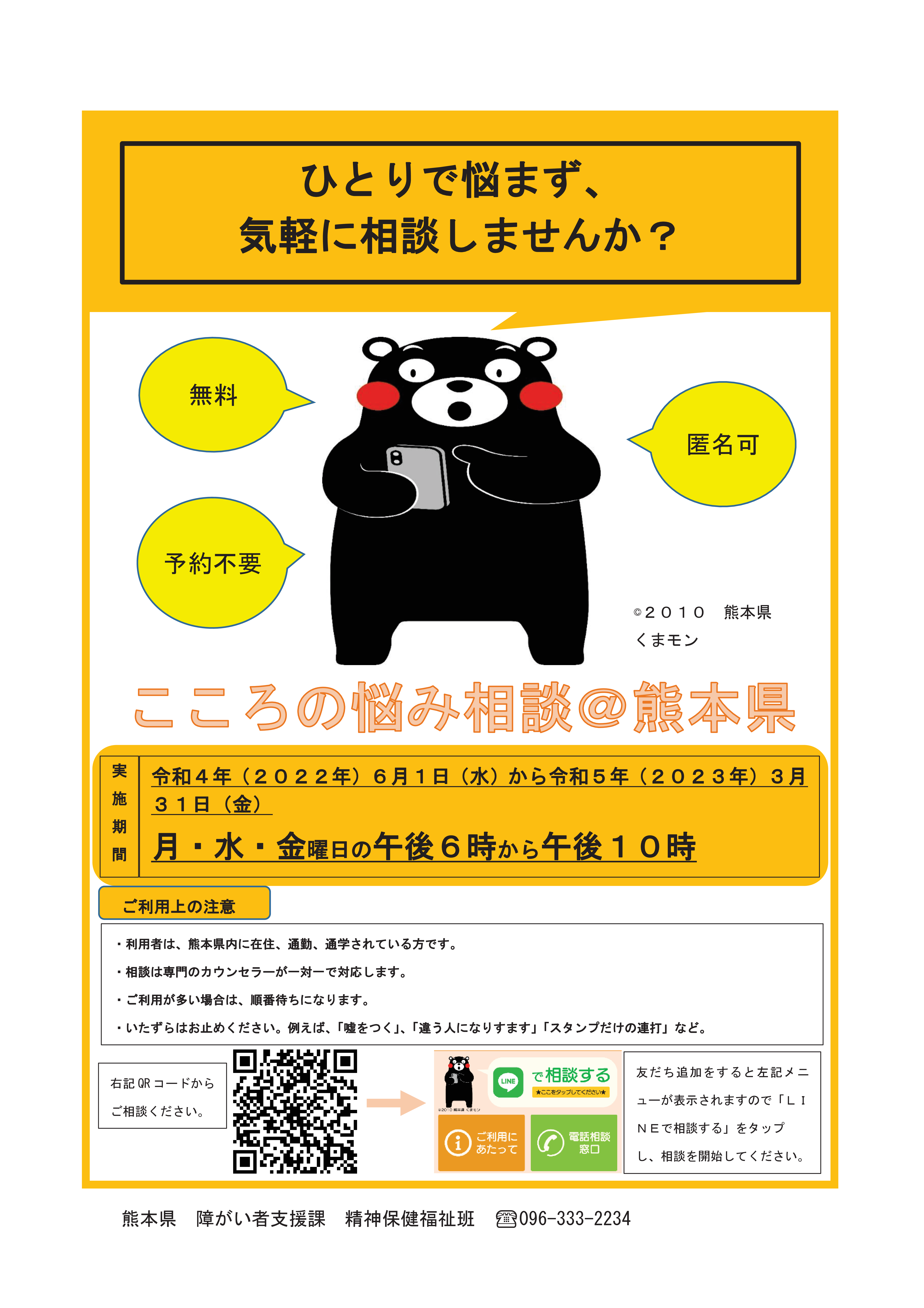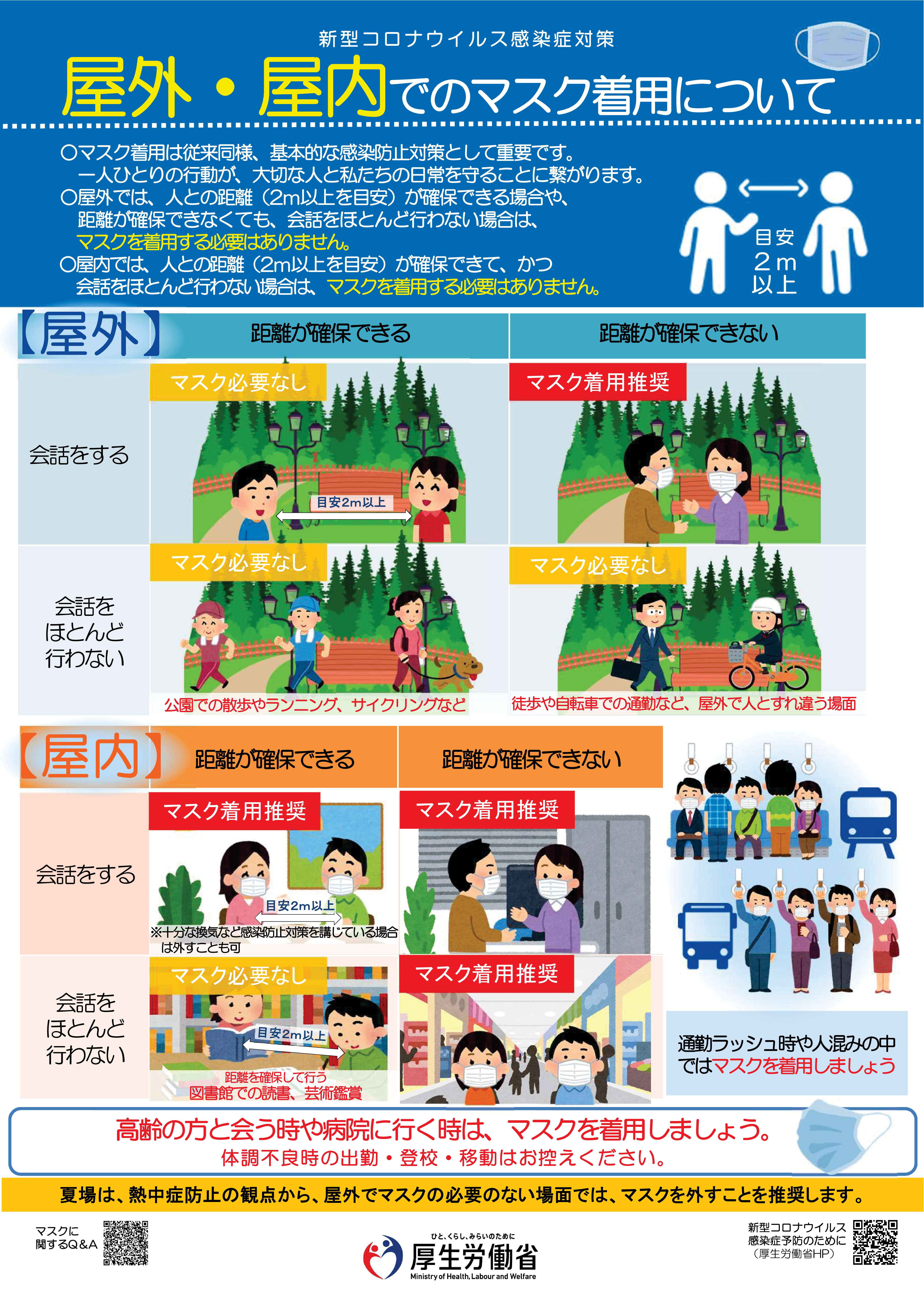労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、特化則、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル則」という。)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)(以下特化則、有機則、鉛則及び粉じん則を「特化則等」と総称する。)、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)並びに化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第133号。以下「告示」という。)について、所要の改正が行われました。
改正のポイント!
(1)事業場における化学物質の管理体制の強化
化学物質管理者の選任 (安衛則第12条の5関係)
保護具着用管理責任者の選任 (安衛則第12条の6関係)
雇入れ時等における化学物質等に係る教育の拡充 (安衛則第35条関係)
(2)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
SDS等による通知方法の柔軟化 (安衛則第24条の15第1項及び第3項※、第34条の2の3関係)※公布日時点においては第24条の15第2項
「人体に及ぼす作用」の定期確認及び「人体に及ぼす作用」についての記載内容の更新 (安衛則第24条の15第2項及び第3項、第34条の2の5第2項及び第3項関係)
SDS等における通知事項の追加及び成分含有量表示の適正化 (安衛則第24条の15第1項、第34条の2の4、第34条の2の6関係)
化学物質を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化 (安衛則第33条の2関係)
(3)リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
リスクアセスメントに係る記録の作成及び保存並びに労働者への周知 (安衛則第34条の2の8関係)
化学物質による労働災害が発生した事業場等における化学物質管理の改善措置 (安衛則第34条の2の10)
リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置等の事業者の義務 (安衛則第577条の2、第577条の3関係)
保護具の使用による皮膚等障がい化学物質等等への直接接触の防止 (安衛則第594条の2及び安衛則第594条の3※関係) ※令和3年4月1日時点においては第594条の2
(4)衛生委員会の付議事項の追加 (安衛則第22条関係)
(5)事業場におけるがんの発生の把握の強化 (安衛則第97条の2関係)
(6)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規則の適用除外 (特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛規則第3条の2及び粉じん則第3条の2関係)
(7)作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置の強化
作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務 (特化則第36条の3の2第1項から第3項まで、有機則第28条の3の2第1項から第3項まで、鉛則第52条の3の2第1項から第3項まで、粉じん則第26条の3の2第1項から第3項まで関係)
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務 (特化則第36条の3の2第4項、有機則第28条の3の2第4項、鉛則第52条の3の2第4項、粉じん則第26条の3の2第4項関係)
作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務 (特化則第36条の3の2第5項、有機則第28条の3の2第5項、鉛則第52条の3の2第5項、粉じん則第26条の3の2第5項関係)
記録の保存
(8)作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和 (特化則第39条第4項、有機則第29条第6項、鉛則第53条第4項及び四アルキル則第22条第4項関係)
施行日及び経過措置
改正省令及び改正告示は、公布日から施行となります。ただし、一部の規定及び当該規定に係る経過措置については、令和5年4月1日、令和6年4月1日から施行されます。
改正省令(改正省令第1条を除く。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によります。
細部事項等については以下のリンクからご覧いただくことができます。
(別添)_労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について_.pdf
また、当センターでは化学物質管理についての産業保健研修会を予定しておりますので、ぜひご参加ください。(申込受付けは開催日の一カ月前からとなります。)
産業医向け
8月9日 化学物質対策の転換点【産医単位:専門1.5】 くまもと県民交流館パレア 会議室1
一般・事業場向け
10月4日 《オンライン研修》 化学物質対策の転換点
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介【労働安全衛生総合研究所】
(過去記事)化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が見直されます