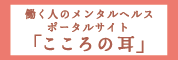2022年12月アーカイブ
厚生労働省は、12月26日、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いました。
今年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。
■告示のポイント
|
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物の うち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年 3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。 ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。 ・エタノール ・特別管理物質※ ※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質 2 適用日 令和5年4月1日 |
熊本労働局(局長 新田 峰雄)では、このたび、令和4年「高年齢者雇用状況等報 告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。
今回の集計結果は、従業員21人以上の企業3,303社からの報告に基づき、このような 高年齢者の雇用等に関する措置について、令和4年6月1日時点での企業における実 施状況等をまとめたものです。
|
【集計結果の主なポイント】 Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況 ① 高年齢者雇用確保措置の実施状況(10ページ表1、11ページ表3-1) 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は3,295社(99.8%)[0.6ポイント増加] ・企業規模別には中小企業では99.7%[0.6ポイント増加]、大企業では100.0%[変動なし] ・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、 全企業において67.6%[1.8ポイント減少] ② 65歳定年企業の状況(12ページ表4) 65歳定年企業は793社(24.0%)[1.6ポイント増加] ・中小企業では24.5%[1.7ポイント増加] ・大企業では13.3%[1.3ポイント減少] Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況 ① 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況(13ページ表5-1) 70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 889 社(26.9%)[3.1 ポイント増加] ・中小企業では 27.6%[3.2 ポイント増加] ・大企業では13.9%[1.2ポイント増加] ② 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況(14ページ表6) 66歳以上まで働ける制度のある企業は1,419社(43.0%)[3.4ポイント増加] ・中小企業では43.4%[3.5ポイント増加] ・大企業では34.8%[2.5ポイント増加] ③ 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況(14ページ表7) 70歳以上まで働ける制度のある企業は1,347社(40.8%)[3.5ポイント増加] ・中小企業では41.1%[3.5ポイント増加] ・大企業では33.5%[2.5ポイント増加] ④ 定年制廃止企業等の状況(12ページ表4) 定年制の廃止企業は 100 社(3.0%)[0.2 ポイント増加] ・中小企業では 3.2%[0.2 ポイント増加] ・大企業では0.0%[変動なし]
※この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。 |
詳細は、以下のリンクをご覧ください。

令和4年「高年齢者雇用状況報告」の集計結果を公表します(全国版)【厚生労働省】
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果
~MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加します~
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年1月中旬の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めます。
【改正のポイント(別添3参照)】
健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。
このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の製造・取扱業務を追加等するものです。
【改正の内容】
・健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAの製造・取扱業務を追加
・健康管理手帳の交付対象要件を、MOCAの製造・取扱業務に2年以上従事した経験を有することとする
もの
令和3年度に引き続きオンライン形式で研修を開催いたします。(※計7回を予定しております。)
各回の開催日程及び募集期間は以下のとおりです。
応募多数の際は、先着順ではなく抽選を行いますので、受講を希望される回の募集期間内にご応募ください。
| 開催回 | 定員 | 動画配信研修受講期間 | WEBライブ講習受講日 | 募集期間 | 結果通知 |
| 第6回 | 800名程度 | 1月12日(キ)~2月1日(水) | 2月7日(火)13:00~15:30(予定) |
12月6日(火)13時~ 12月19日(月)17時まで |
12月27日 (火) |
|
第7回 |
800名程度 | 1月27日(金)~2月16日(木) | 2月22日(水)13:00~15:30(予定) |
|
お申し込みはこちら ※クリックしますと、「株式会社ステージ」のサイトにリンクします。 |
|
「令和4年度両立支援コーディネーター基礎研修」申込事務局 Email:johasryoritu2022@stage.ac TEL:03-5966-5779 (10:00~17:00※土日祝・8/12・12/29~1/3を除く) |
|
「認定医療ソーシャルワーカーポイント」申請に関してのお問合せは、以下のアドレスまでご連絡ください。 e-mail:co-ryoritu@honbu.johas.go.jp |
お役立ち情報ー特殊健康診断実施機関一覧を更新いたしました。
最新版は令和4年12月2日付です。
変わらない場合は、キーボードの「F5」を押すか、ブラウザで右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。
第15回じん肺診断技術研修の開催について
※本研修を全て受講しますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位(生涯単位のみ)のほかに、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)も取得できます。
1 目的
じん肺健康診断に従事する医師に対して必要な法制度の知識及び専門技術を修得いただくことを目的とする
2 名称
第15回じん肺診断技術研修
3 実施機関等
主催 独立行政法人労働者健康安全機構
後援 一般社団法人日本職業・災害医学会
4 期間
令和5年2月9日(木)から10日(金)までの2日間
5 開催場所
独立行政法人労働者健康安全機構本部 1階大会議室
所在地 〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
TEL 044-431-8641(問合せ先:勤労者医療課)
6 研修日程
「第15回じん肺診断技術研修日程表」のとおり
7 募集人数
40名
8 受講資格
じん肺健康診断等に携わる医師
9 受講料
33,000円 納付方法は受講案内時に御連絡いたします
10 取得単位数
(1)日本医師会認定産業医制度認定単位 9.5単位
※生涯単位のみ、申請中
(2)日本職業・災害医学会認定補償指導医認定単位 2単位
※選択単位 業務上疾病の労災補償
11 申込手続
受講を希望される方は、第15回 じん肺研修受講申込書.(クリックしたらダウンロードします)もしくは労働者健康安全機構のHP(http://www.johas.go.jp/)から受講申込書をダウンロードし、必要事項を御記入の上、記載されているメールアドレス宛てにお申し込みください ※FAX、電話によるお申込みは受付しておりません。
12 申込締切日
令和4年12月27日(火)
ただし、定員に達した時点で申込受付を終了します
13 受講者への通知
受講の決定は申込受付順で行い、受講決定者には受講案内を送付します
定員に達し受講できない方については、その旨を申込時のメールアドレスに御連絡します
14 その他
(1)昼食について
各自で御用意ください
関東労災病院の売店及び食堂以外に、研修会場近隣に売店等はございません
(2)宿泊施設について
各自で御手配ください
15 問合せ先
独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 勤労者医療課
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
TEL 044-431-8641
FAX 044-411-5531
(土曜、日曜、祝日を除く)10:00~12:00、13:00~17:00
今年5月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、作業場所が第三管理区分と区分された場合の規制が強化されました。第三管理区分とは、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態です。
これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられました。
この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めたものです。
■告示のポイント
|
1 有機溶剤等の濃度測定 個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や 個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。 2 有効な呼吸用保護具の使用 有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の 何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。 3 呼吸用保護具の適切な装着の確認 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と 呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタ を上回っていることを確認することを規定。 |
 別添1 告示の概要[PDF形式:657KB]
別添1 告示の概要[PDF形式:657KB]