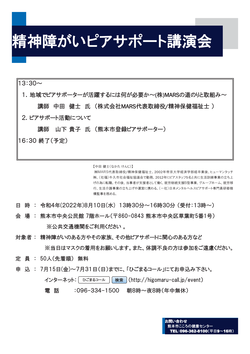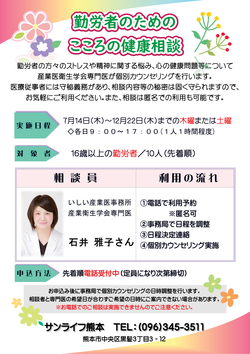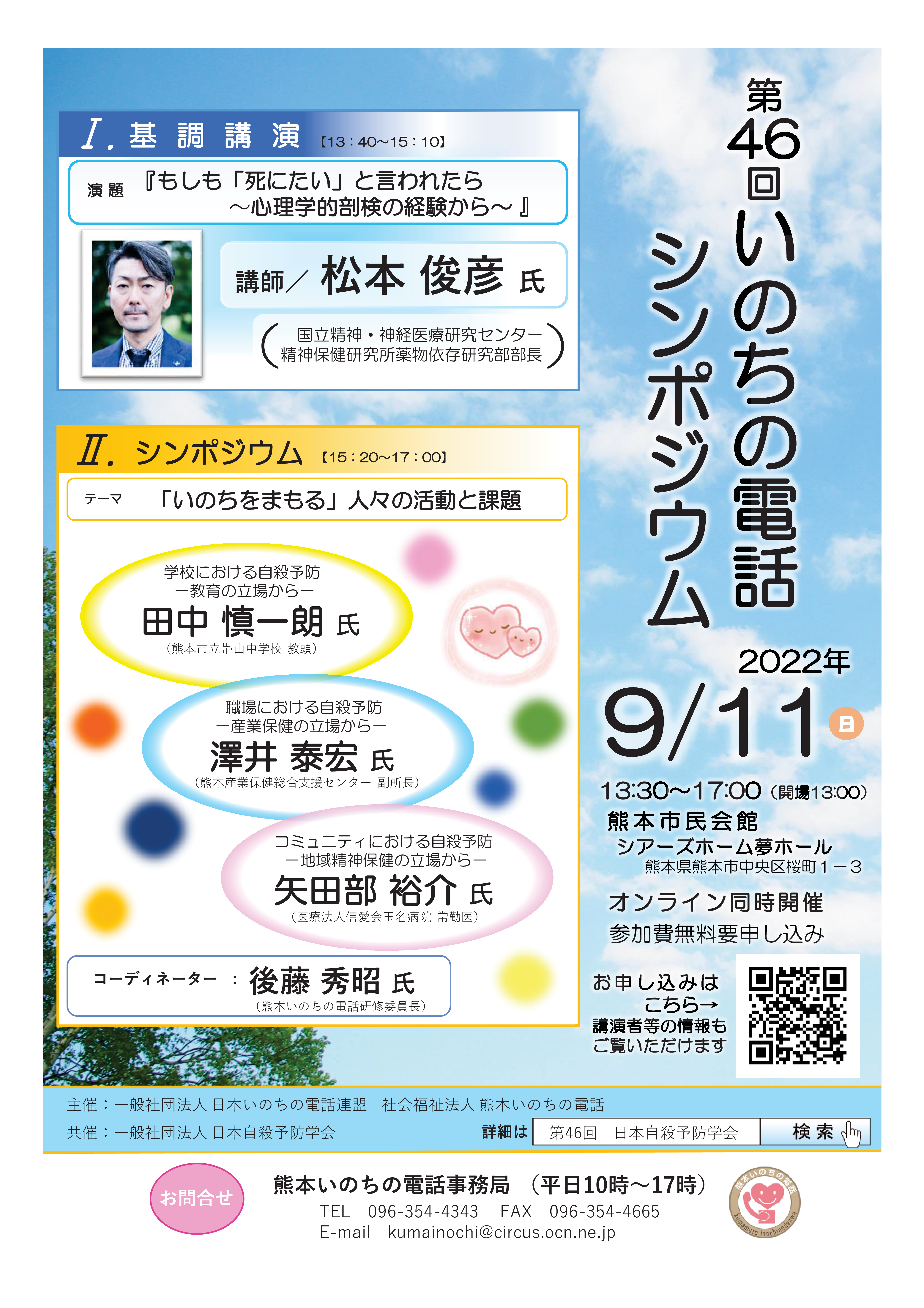厚生労働省から、「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめられ公表されました。
【調査結果のポイント】
[メンタルヘルス対策(注1)への取組状況]<事業所調査>
過去1年間(令和2年11月1日から令和3年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は10.1%(令和2年調査9.2%)。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、労働者数50人以上の事業所で94.4%(令和2年調査92.8%)、労働者数30~49人の事業所で70.7%(同69.1%)、労働者数10~29人の事業所で49.6%(同53.5%)
ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は76.4%(令和2年調査 78.6%)であり、その中で分析結果を活用した事業所の割合は79.9%(同79.6%)
[化学物質のばく露防止対策への取組状況]<事業所調査>
労働安全衛生法第57条の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は69.9%(令和2年調査53.6%)
労働安全衛生法第57条の2の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は77.9%(同62.2%)
[建築物における吹付石綿等の処理状況]<事業所調査>
事業所にむき出しの状態の吹付材等がある事業所の割合は2.9%。このうち、石綿が使用されている吹付材等がある事業所の割合は19.5%。
[産業保健に関する状況]<事業所調査>
過去1年間(令和2年11月1日から令和3年10月31日までの期間)に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は66.1%。
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は41.1%。両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合は79.9%であり、このうち、困難や課題と感じている内容をみると、「代替要員の確保」が70.5%と一番高い。
[高年齢労働者・外国人労働者に対する労働災害防止対策への取組状況]<事業所調査>
60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所(割合 75.6%)のうち、高齢者への労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は78.0%(令和2年調査81.4%)で、本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は41.4%(同45.7%)
外国人労働者が従事している事業所(割合 15.5%)のうち、外国人労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は87.5%(同89.8%)であり、定期的に必要な健康診断を受診させている事業所の割合が59.8%(同62.3%)
[仕事や職業生活に関する強いストレス]<個人調査>
現在の仕事や職業生活に強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%(令和2年調査54.2%)、その内容は「仕事の量」が43.2%(同42.5%)と最も多い。
現在の自分の仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は92.1%(同90.3%)であり、相談できる相手は「家族・友人」が80.1%(同78.5%)と最も多いが、ストレスについて相談できる相手がいる労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は69.8%(同74.1%)
[喫煙に関する事項]
職場で受動喫煙がある労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」8.4%(令和2年調査7.6%)、「ときどきある」12.3%(同12.5%)を合わせ20.7%(同20.1%)
(注1)事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置をいう(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)
その他詳細な調査結果は以下のリンクからご覧ください。
令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表します【厚生労働省ホームページ】